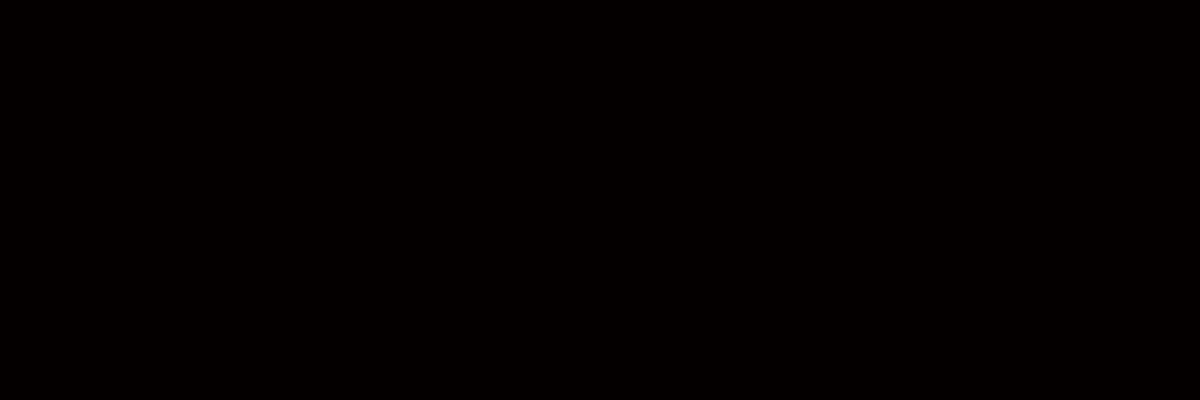AIによる投資のメリットとデメリットとは
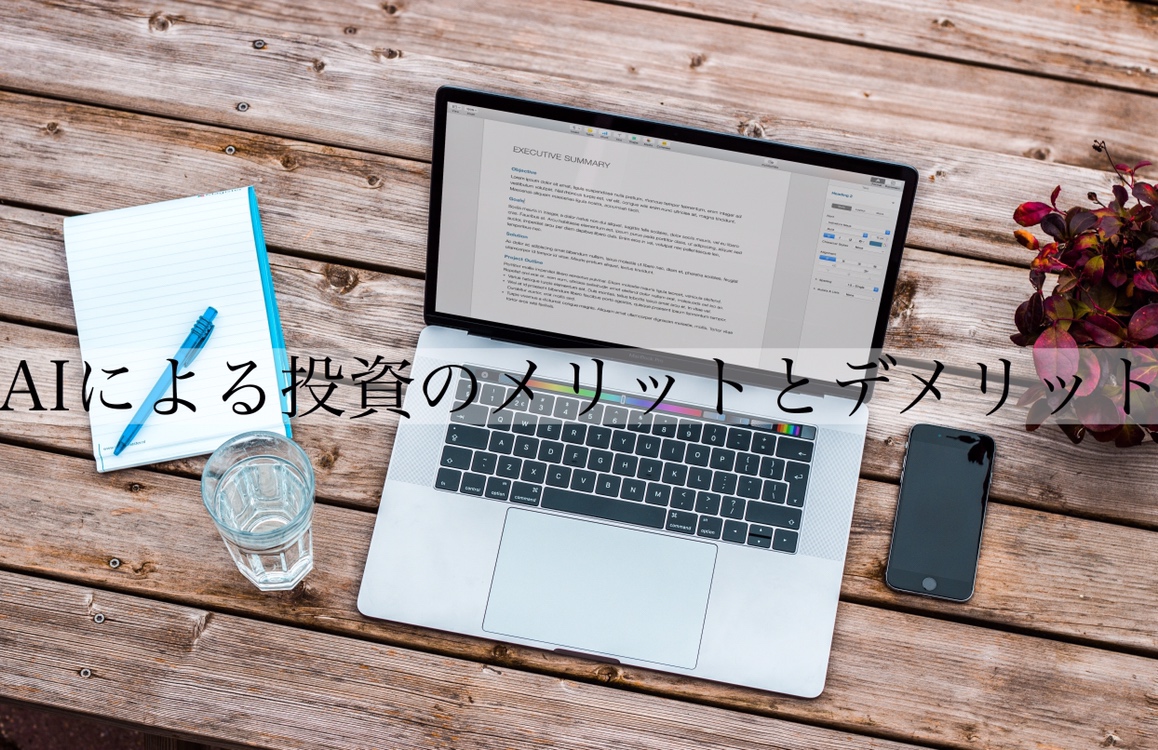
AI技術の発展はよくも悪くも人間の世界に大きなイノベーションをもたらそうとしています。
考えられるメリットは、人間の頭脳ではできないような緻密な計算を瞬時にできることや膨大な量のデータを光の速さで処理することができることなどが挙げられます。
デメリットとしては、AI技術がありとあらゆる分野に侵入し世の中を席巻することで人間の仕事を奪い去ってしまうことでしょう。
投資の世界でも当然AI技術の参画は進められていますが、現状はどのような状況になっているのでしょうか。見ていきましょう。
ヘッジファンドの資産の2~7%程度がAI運用になっていく

巨大ヘッジファンド、ツーシグマ創業者の個人資産を運用していたリシ・ガンティ氏は以下のように述べています。
「アルゴリズムがわれわれの職を奪おうとしている。アルゴリズムは電力のみで読むことも処理することもでき、光が人間の目に届く頃にはもう取引が完了している」
ガンティ氏は毎年ヘッジファンドの資産の2~7%程度が、徐々にAIによる運用へと移り変わっていくことも示唆しています。
危惧すべき日本人の金融リテラシーのなさ

アメリカなどでは、小さい頃から金融リテラシーについて勉強をさせられます。
小学生の頃からお金に対する授業のコマが設けられているのです。
そのため、大学生や社会人になるとほとんどの人が投資を行うという環境が整えられています。
一方、日本ではそのような教育環境は一切整えられていません。
むしろ「投資は怖いものだ」と言う間違った認識が浸透してしまっています。
それを表すように、日本人の7割は銀行から勧められた投資信託を言われるがままに購入し、損失を出してしまっているというデータすらあるほどです。
投資の成功には人間感情を読み取らなければならないという側面がある

なぜこれほどまでに多くの人間が投資で失敗してしまっているのでしょうか。
それは、日本人の「右にならえ」の性分が大きく関わっていると考えられます。
多くの人が「銀行員はお金のプロフェッショナルであり、資産運用に相談するに値する」と認識しています。
しかし、それは大きな間違いです。
銀行員といってもいち会社人であり、当然ノルマがあります。
ノルマを達成するために、時にその人に合わない投資商品を無理矢理売り付けることもあります。
そんな時の謳い文句の1つに、「みんなががやっているから安心です」という口上があります。
投資の大原則は、「人が買わないときに買い、人が買いたいときに売る」です。
“みんながやっているから投資をやってみる”。もちろん投資を始めるきっかけとしてはそれで良いのかもしれませんが、自分の頭で考えることを放棄してただただ言われるがままに投資を行っているようでは、日本人の7割が投資で失敗しているという事実にもうなずけます。
投資を成功させるのに最大の秘訣は、「人間の心理や感情を読み取り、いかに人と違う行動を取れるか」というところにあります。
大衆心理を読み解くことは、投資の成功に必要不可欠なのです。
AIには人間の感情が読み取れない

さて少し話がそれたが、AIの話に戻します。
AIは、機械の力で人間だからこその過ちを犯すことはありません。ヒューマンエラーとは程遠い存在です。
技術の進歩でどんどん運用もAIに置き換わり、進歩の結果、「100%勝てる投資も実現するのではないか?」とまで考えられました。
しかし、残念ながら、いまだAIによる資産運用は結果を出すに至っていません。
AIを使用する12のヘッジファンドで構成されているユーリカヘッジAIヘッジファンドの指数は、2013年以降、ヘッジファンド総合の指数を上回ってはいるものの、S&P500種株価指数のリターンには及ばないのです。
確かに膨大な量のデータを駆使し、株価が上がったら買う、株価が下がったら売るなどという単純なスキームをこなすことはAIの方が圧倒的に得意です。
しかし、先述の通り投資において市場の雰囲気を正確につかみとり人間心理を投資に応用することもまた非常に重要なこと。
にもかかわらず、AIにはそのような投資手法をこなすことがまだできないのです。
現場のAI技術ではまだ人間の方が分があるという部門も数多く存在し、トータルで見れば最終決定を人間に任せる方が投資効率は良いと考えられています。
ダブルライン・キャピタルのCEOである、ジェフリー・ガンドラック氏も「機械が金融の世界を牛耳ることはなく、人間が勝つ」との述べています。
もちろんAI技術は投資の世界の発展にも大きな役割をもたらすはずです。
AIの良いところは、よくも悪くも感情がなく淡々と素早い計算ができるところ。この技術はなくてはならないものでしょう。
しかし人間の感情が市場を大きく左右する投資の世界では、それだけでは到底通用しません。
これからは、人間とAIの作業分担について考えていかなければならないでしょう。